「正社員として内定をもらえたけれど、試用期間ってなに?」
「お試し期間ってことは、簡単にクビになる可能性があるの?」
初めて正社員として働く方や転職を考えている方にとって、勤め先に「試用期間」があると、このような疑問や不安を感じてしまうことがあると思います。
そこで本記事では、試用期間の基礎知識や、トラブルを防ぐためのポイント、円満に退職するための手続きなどをまとめました。安心してキャリアの第一歩を踏み出したいという場合は、ぜひお読みください。
わくスタでは「休みを取りやすい」「福利厚生が充実している」など、好条件の求人をたくさんご用意しています。最新情報を公式LINEで発信していますので「自分にぴったり合う仕事を見つけたい」とお考えの方は、下記のボタンから友だち登録してみてください。
試用期間とは?

まずは、正社員の試用期間の基本的な部分から見ていきましょう。
目的と期間
試用期間とは、簡単にいうと働く人と会社が、お互いの相性を確認するための期間のことです。会社は、面接だけでは分からない「自社の社風や業務内容に合っているか」「長く活躍してくれそうか」といった実務的な適性を評価しています。
一方で、働く人にとっても「聞いていた仕事内容とギャップはないか」「この会社で、無理なく働き続けられそうか」などを見極めるための大切な期間でもあります。試用期間の長さは法律で定められているわけではありませんが、3ヶ月と定めている企業が一般的で、長くても6ヶ月程度です。
試用期間が6ヶ月ある場合の注意点は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
雇用形態と待遇
「試用期間中はまだ正社員ではないのでは?」と心配になるかもしれません。ですが法的には、入社日から会社と正式に雇用契約を結んだ正社員として考えられます。専門的には「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、通常の労働契約と同じように法的に保護されています
試用期間中の一般的な待遇は、下記のとおりです。
| 給与 | 本採用時と同じ金額が支払われるのが基本。企業によっては試用期間中のみ少し低い給与額を設定している場合がある |
| 残業代 | 時間外労働をした分の残業代は、全額支給される |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険といった社会保険は、入社日から加入する |
| 福利厚生 | 交通費などの福利厚生は、基本的に利用できる |
| 有給休暇 | 試用期間も勤続年数に含め、入社日から6ヶ月が経過した時点で付与される |
例えば給与は、本採用時と同じ金額が支払われるのが基本ですが、企業によっては試用期間中のみ少し低い給与額を設定している場合があります。その場合でも、必ず雇用契約書に明記されている必要があり、最低賃金を下回ることは許されません。
また、時間外労働をした分の残業代は、試用期間中であっても全額支給されます。試用期間の雇用形態・待遇などについては以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
解雇のルール
「試用期間中にミスをしたら、クビにされるかもしれない」と考える方もいますが、その心配は基本的に不要です。試用期間中であっても、会社は従業員を一方的に解雇することはできません。
解雇が認められるのは、「客観的に見て合理的な理由」があり、社会通念上相当と認められる場合に限られます。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働契約法|e-Govポータル
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 履歴書に虚偽があることが発覚した
- 正当な理由なく、何度も無断で欠勤を繰り返している
- 協調性が著しく欠けており、注意しても改善せず、業務に支障をきたしている
「一度だけ遅刻してしまった」「仕事の覚えが少し遅い」といった理由だけで解雇されることはありません。会社側にも、社員を教育・指導する義務があるため、改善の機会を与えずにいきなり解雇することは、原則認められません。
解雇の条件については以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
試用期間が終了した後の流れ
多くの場合、試用期間が終了しても特別な手続きはなく、自動的に本採用へと移行します。そのため基本的には、何かを申請する必要はなく、そのまま仕事を続けていれば問題ありません。
ただし、会社によっては「本採用通知書」や「労働条件通知書」などを改めて渡される場合があります。その際は、給与や勤務時間、休日などの労働条件が、入社前に聞いていた話や雇用契約書の内容と変わりないか、念のため自分の目でチェックするようにしましょう。
試用期間のトラブルを防ぐ3つのポイント
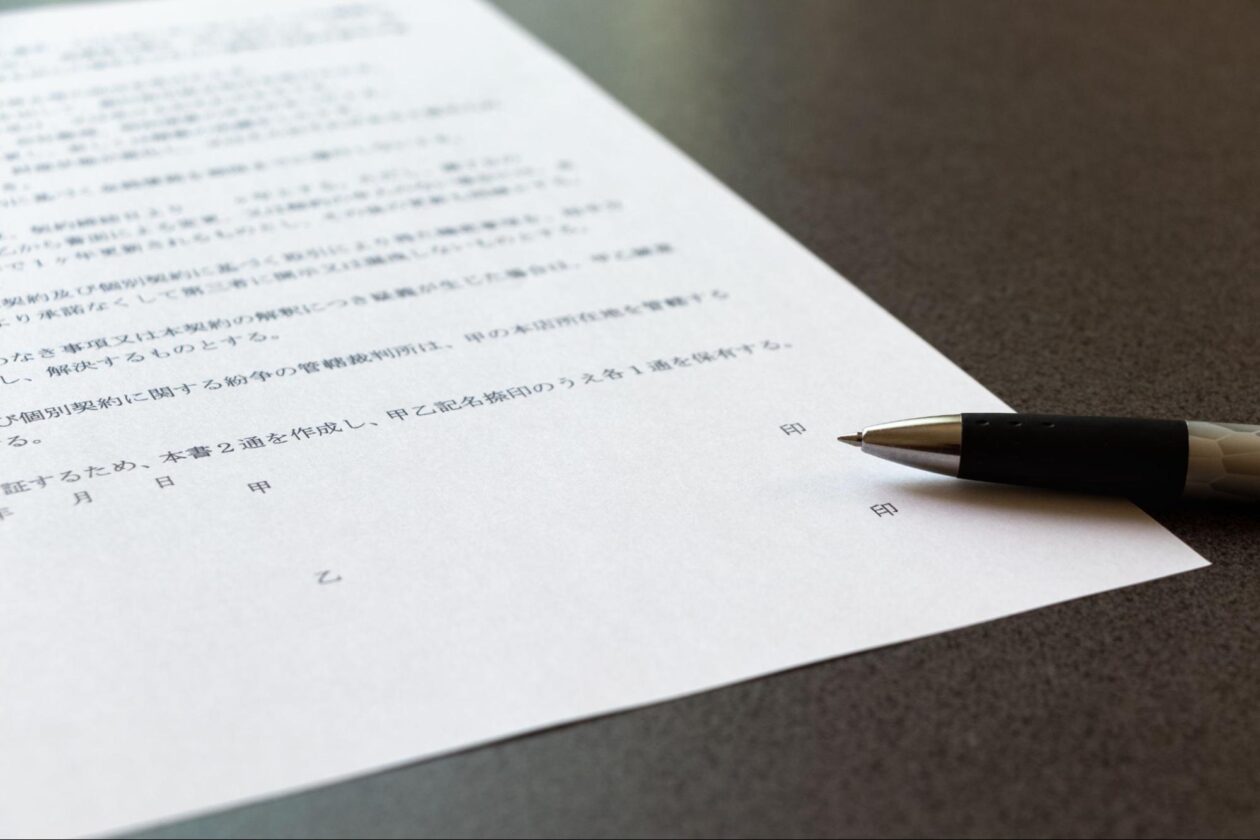
試用期間を迎えるにあたっては、事前に次の3つのポイントを押さえておくことで、無用なトラブルを防げます。
- 雇用契約書の内容を確認する
- 会社の「評価基準」を把握しておく
- 「辞める選択肢もある」と知っておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ポイント1. 雇用契約書の内容を確認する
入社手続きの際に「雇用契約書」を渡されたら、以下の項目が明記されているか、必ず確認してください。
- 試用期間の有無
- 試用期間の開始日と終了日
- 試用期間中の給与額
- 本採用後の給与額
- 試用期間が延長される可能性の有無とその条件
もし記載内容に不明な点や、面接で聞いていた話と違う点があれば、人事担当者に質問しましょう。言い出しにくいかもしれませんが、「恐れ入ります、給与の項目について、認識が合っているか確認させていただいてもよろしいでしょうか?」のように丁寧に聞けば、失礼にあたることはないので安心してください。
ポイント2. 会社の「評価基準」を把握しておく
試用期間中は、「会社からどのように見られているんだろう?」「何をどこまでできれば良いんだろう?」と不安になるものです。その不安を解消するために、はじめに会社のゴールを具体的に把握しておくことをおすすめします。
配属後の上司との面談の際に、以下のように質問をしてみましょう。
- 試用期間が終わるまでに、私が覚えるべき仕事の範囲はどこまででしょうか?
- この業務では、どのような精度やレベルが求められますか?
自分のやるべきこと・目指すべき場所が明確になれば、日々の目標が立てやすくなり、安心して仕事に集中できます。
ポイント3. 「辞める選択肢もある」と知っておく
試用期間は、会社から評価を受けるだけでなく、働く人も会社を長く働ける組織かどうかを確認するための期間です。万が一、どうしてもこの会社は合わないと感じた場合、無理して働き続ける必要はありません。
スキルが合うかだけでなく、「自由な環境を好むか、チームでの協調性を重視するか」といった価値観や、「フィードバックを前向きに捉え、成長の糧にできるか」といった仕事への心構えが合うかも重要な判断基準です。
いざとなったら、退職するという選択肢もあると考えていれば、精神的に追い詰められることなく、心に余裕が生まれます。このように考えることで、目の前の仕事にリラックスして取り組めて、楽しくなることもあります。
試用期間中に退職したくなったときの手続きの流れ

どうしても試用期間中に退職したくなったときは、正しいステップを踏むことで円満な退職を目指すことができます。ここでは、そのための具体的な4つのステップを詳しくお伝えします。
- 上司にアポイントを取る
- 退職の意思を口頭で伝える
- 退職届を提出する
- 引き継ぎをおこなう
それでは、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1. 上司にアポイントを取る
最初にすべきことは、直属の上司に相談の時間を確保してもらうことです。
いきなり退職届を出すのではなく、まずは「相談したいことがあるのですが、少しお時間をいただけますでしょうか?」と声をかけ、会議室など他の人に会話が聞こえないような場所をセッティングしてもらいましょう。
ステップ2. 退職の意思を口頭で伝える
上司に時間を確保してもらったら、「退職したい」という意思を自分の言葉で直接、かつ明確に伝えます。このとき、退職理由について質問を受ける可能性が高いですが、会社の給与や人間関係への不満を感情的にぶつけるのはおすすめしません。
これまでお世話になったことに感謝する気持ちを持って、あくまで自分自身の都合として伝えるようにしましょう。
▼例文
本日はお時間をいただきありがとうございます。大変申し上げにくいのですが、〇月〇日で退職させていただきたいと考えております。
実務に携わるなかで、当初想定していた自身のキャリアプランとの間に少し差ががあると感じたため、あらためて自分の適性を見つめ直したいと思っています。
ここまで大変お世話になったなか、このようなお願いで申し訳ございません。
ステップ3. 退職届を提出する
上司と話し合い、退職日が正式に決まったら、会社の就業規則に従って退職届を提出します。会社に指定されたフォーマットがなければ、自分で作成しましょう。このとき、退職届に書く退職理由は、シンプルに「一身上の都合により」と記載すれば問題ありません。
ステップ4. 引き継ぎをおこなう
たとえ短い期間であったとしても、あなたが担当していた業務は存在します。そのため、後任の人やチームのメンバーが困らないよう、仕事の内容と進捗状況を資料にまとめたり、口頭で丁寧に説明したりして、責任をもって引き継ぎをおこないましょう。
最後まで責任を果たす姿勢が、これからの社会人としての信頼につながり、良好な関係を保ったまま次のステップへ進めます。試用期間が満了したあとの退職については以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
試用期間に関するよくある質問

最後に、試用期間に関してよくある質問にお答えします。
Q1. 試用期間中に有給休暇は取得できる?
試用期間中に有給休暇を取得できるケースは少ないです。法律で定められた有給休暇の付与条件が、試用期間を含めて入社日から6ヶ月が経過し、全労働日の8割以上出勤した時点となっているためです。
(年次有給休暇)
出典:労働基準法|e-Govポータル
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
例えば試用期間が3ヶ月の場合、その期間中にはまだ有給休暇は発生していないと考えられます。体調不良など、どうしても仕事を休む必要があるときは、有給休暇ではなく欠勤扱いになるのかなど、必要な対応を上司に確認しましょう。
有給休暇の付与日数やルールなどについては以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
Q2. 試用期間中に退職することはできる?
法律上は、試用期間中でも2週間前までに意思を伝えれば、退職することが可能です。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法|e-Govポータル
ただし、会社への影響を最小限に抑えるためには、引き継ぎなどを考慮して1ヶ月ほど前に伝えることが理想的です。
Q3. 試用期間で退職したら、履歴書に書かなくてよい?
試用期間で退職したとしても、職歴として記載するのが原則です。
会社に在籍したことは事実なので、記載しないと「経歴詐称」と判断されるリスクがあります。転職活動をする際も、正直に事実を伝え、前向きな退職理由を説明できれば、採用担当者に理解してもらえるはずです。
履歴書への書き方や注意点については以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。
Q4. 試用期間が延長されることはある?
可能性は低いですが、ゼロではありません。
ただし、延長が認められるには、「雇用契約書や就業規則に延長の可能性が記載されていること」と、「病気による長期欠勤で評価が困難だった」など客観的で合理的な理由がある場合に限られます。会社が一方的に延長することはできず、従業員の同意も必要となるケースが一般的です。
まとめ:試用期間を正しく理解し、安心して働き始めよう!

この記事では、正社員の試用期間について、その法的な位置づけや待遇といった基礎知識から、トラブルを防ぐためのポイント、退職したいときの手続きまでを詳しく解説しました。
試用期間は、働く人と会社がこれから長く良好な関係を築いていけるか、お互いの相性を確かめるための大切な期間です。「この会社で自分は本当に活躍できるか」を見極める気持ちで、あまり気負いすぎずに、前向きな姿勢で臨んでみてください。
わくスタでは「休みを取りやすい」「福利厚生が充実している」など、好条件の求人をたくさんご用意しています。最新情報を公式LINEで発信していますので「自分にぴったり合う仕事を見つけたい」とお考えの方は、下記のボタンから友だち登録してみてください。


